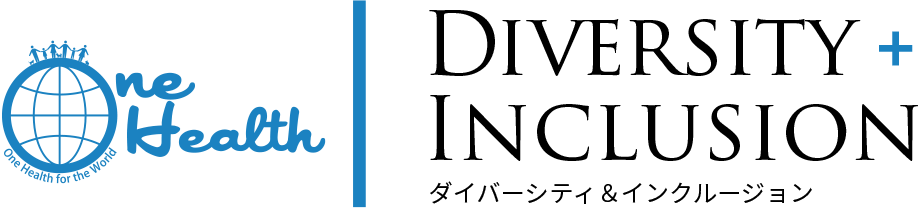-
キャリアもプライベートも、留学したからこそ今の自分がある

日本医科大学
眼科学教授
多摩永山病院 眼科部長 堀 純子 氏- 日本医科大学しあわせキャリア支援センター委員を兼務し、ダイバーシティ補助事業(女性リーダー育成型)でグローバル⼈材の育成や海外での研究⽀援についての検討に携わる堀純子氏に、女性リーダー育成を通じたダイバーシティ研究環境づくりの意義を聞きました。(構成:木村麻紀/ジャーナリスト) 2023年10月27日インタビュー
- ― 女性リーダー育成を通じたダイバーシティ研究環境の実現に向けて、なぜグローバルな研究支援が必要なのでしょうか。
- 政府は2020年までに女性管理職の比率を30%にする目標を掲げましたが、達成できずに2030年まで延ばしました。2023年の日本のジェンダーギャップ指数は世界146カ国中125位で過去最低です。日本で女性リーダーが増えにくいのはなぜか―。真のリーダーシップを発揮できる人材が現場に少ないからです。能力が足りないのではなく、日本特有の社会構造の中で、出産・育児といった女性特有のライフイベントの際にキャリアの中断や断念を余儀なくされてきた長い歴史のためです。医師になって33年、女性はライフイベントに直面すると、大学の常勤職を辞める、研究を辞めなければならないという状況をずっと見てきました。女性のポテンシャルが高くても、上位職になるキャリアパスから外れてしまった人が多く、現時点で急に増やそうとしても実績を持った人が少ないのです。
- そこで、多くの企業や大学で今行われているのが、女性の上位職への早めの登用、いわゆるポストアップです。組織側が見守りながら、数年以内に昇任が可能と評価された女性候補者を早めに引き上げる制度で、何とか数合わせ的に役職につけているのが現状です。
- 多様性を推進していく方向へ日本の社会構造を変革するためには、国内で要職にある人に引き上げてもらうだけでなく、グローバルな視点から日本はここがおかしい、もっと多様性が必要だと発言できる女性が30%いないと変革できません。そのような真の女性リーダーを育成するためには、必ずグローバルな場を経験してもらうことが重要だと思います。
- 私たち医師・研究者が国際的に認められるためには、M.D.とPh.D.という学位とともに、それぞれの研究領域でのグローバルな人的ネットワークが必須です。大学の講師以上になるためにはPh.D.(博士号)は必要ですが、厳密に言えば、どこの大学でPh.D.を取得し、どのような論文実績があり、どこでポストドクター(博士研究員)を終了したか、有名ラボで活躍したかどうかを学歴と職務経歴書で評価されます。さまざまな国から優秀な人材が集まって一緒に研究するコミュニティのメンバーになることは、帰国後に自国でリーダーシップを取る上で大きな支えになります。大きなラボで研究の知識や技術とともに、資金・人の集め方など広い意味で研究力を身につけると、帰国してジュニアリーダとしてスタートしても能力を発揮できます。このようなキャリアは、アカデミックな信用力の基盤になり、研究者としての自信にもつながります。
- 一方で、家庭の事情や経済的に留学するのが難しい人には、国際学会での発表という機会があります。これも非常に大きな刺激を得られる場です。私も学会プログラムを作る側として関わったことがありますが、国際学会では登壇者の決定に当たって女性や人種の多様性を担保することが義務づけられています。若手がシニアに質問することも普通です。日本ではまだまだですが。
- ー グローバル⼈材育成のための支援制度である女性研究者海外研修助成(ダイバーシティ支援)と国際学会発表助成について、募集、実施してみて反応はいかがでしたか。
- 期待した通りの応募があり、頼もしいですし、嬉しかったですね。海外研修助成は今後審査を経て決定し、国際学会発表助成は随時募集中です。
- ― 堀先生ご自身も、海外への研究留学を経験されていますが、どのような点が現在の研究や診療に活かされていますか。
- キャリアの面でもプライベートの面でも、留学しなければ今の自分は絶対ありませんでした。留学先の研究所はラボも素晴らしく、全世界から優秀な人材が集まっていました。約半数が女性で、日本とは大きな環境の変化でした。女性はマイノリティでなく、自由に発言できる環境がありました。
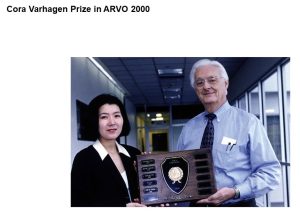 眼科学のみでなく、移植学や免疫学など他領域のラボともミーティングがありましたが、女性教授も多かったです。彼女たちはワークライフバランスを重視していて、夕方5時半になると帰るのでびっくりしました。日本では、深夜や土日にも実験していましたから。
眼科学のみでなく、移植学や免疫学など他領域のラボともミーティングがありましたが、女性教授も多かったです。彼女たちはワークライフバランスを重視していて、夕方5時半になると帰るのでびっくりしました。日本では、深夜や土日にも実験していましたから。- 実は日本にいた当時、私は結婚していましたが、自分は子どもを産まないと思っていました。しかし、米国では多くの女性教授が子育てもしていて、「産んでいいのか!」と思って(笑)、一人目は米国で出産、育児をしました。出産、育児をしていることによる差別的な扱いもなく、女性医師・研究者の自由な生き方に触れて目から鱗が落ちるような思いでした。
- 世界最大級のラボでしたので、当時のポスドクの同僚たちは、現在はそれぞれの母国でリーダー的な存在になって研究領域を引っ張っています。このグローバルな人的ネットワークは、私を国際学会での役職に推薦もしてくれますし、さまざまな困難な場面で激励し助言をくれます。自分のアカデミックな基礎を信じて研究を継続して発信し続ければ、グローバルなネットワークがそれを認めてサポートしてくれる、自分を生かしてくれていると感じています。
- ― 日医大のグローバル研究支援制度は今後、どのような人材に活用して欲しいですか。
- 応募条件は「本学の常勤の女性研究者(助教以上)」で、職位や年代は関係ありません。ライフステージもさまざまだと思いますので、若手や助教になりたての方、シニアの方も応募できるよう、応募条件に自由度を持たせました。留学期間についても、1カ月以上程度にして応募のハードルを下げました。
- 海外での研究や研究発表を経験したり、海外の研究者と交流したりできる留学に、興味をもってチャレンジしてみようというやる気のある人でしたら、どなたでも応募いただきたいですね。それまでの研究経験は問いません。
<プロフィール>
堀 純子先生(ほり・じゅんこ)
日本医科大学 眼科学教授 日本医科大学多摩永山病院 眼科部長1990年に新潟大学医学部を卒業。東京大学医学部眼科学教室の助教を経て、米国ハーバード医科大学スケペンス眼研究所に留学。2001年から日本医科大学に入職し、診療しながら、基礎研究も続けている。2018年から現職。
-
敬譲相和の精神でダイバーシティを推進

日本獣医生命科学大学
学長 鈴木 浩悦 氏
本イニシアティブ連携機関の一つである日本獣医生命科学大学の新しい学長に、鈴木浩悦氏が就任しました。今後の日獣大のダイバーシティ推進で重視する基本的な考え方について聞きました。(構成:木村麻紀/ジャーナリスト) 2022年11月7日インタビュー
- 日本獣医生命科学大学(日獣大)は、1881年に日本初の私立獣医学校として開学しました。獣医学部と応用生命学部に4つの学科があり、先生方も獣医から看護、動物化学、社会科学に至るまで、それぞれに背景や専門性が異なります。こうした多彩な先生方と多様な学生の皆さんが出会い、ともに学びながら、イノベーションの創出につながる場として機能するには、ダイバーシティの推進が極めて重要です。
- 本学の学是には、ダイバーシティを推進する上で拠りどころにできる言葉があります。それは、戦前に作られた学是で今日まで唯一変わらずに残っている「敬譲相和」です。敬譲相和とは、謙譲と協調、慈愛と人倫を育む科学者の創出を目指すということ。自分は一歩引いて他の人を敬い、相互に理解し合いながら協働していくことの大切さを説いています。この言葉を念頭に置きながら、ダイバーシティ推進室が中心となって本イニシアティブと歩調を合わせながら取り組んでいくことになります。
――ダイバーシティ研究環境の推進や女性研究者の活躍増進のための具体策は?
- 本学では、女性研究者を全体の30%に増やす目標に対して、現状21%にとどまっています。このため、特任教授のポスト設置も含めた教授への選抜と若手の採用・昇進の支援を同時に進めていきます。私自身、女性の同僚から良いコメントやアイデアをもらったり、異なる考え方を提案してもらえたりしたことに助けられてきました。選挙で選ばれる役職以外の会議体で、もっと多くの女性を指名していくことも必要ではないかと思います。
- まずは、全教員リストに基づき、個別にどのようなサポートが必要なのか考えているところです。その時に一番難しいのは、他の先生方に理解してもらうことです。同じ能力のある男性教員がいる時になぜ女性なのか、優遇でないか、ということに対して、そうではないと理解してくれる人が増えていかないと、取り組みが一時的で終わってしまいかねません。
- 連携機関による共同研究への研究費補助と研究支援員の配置については、実績が出てきました。今後は、制度の運用をしっかりと整えながら引き続き進めていきたいと考えています。日医大とは研究分野が異なるので、逆にもっと色々と一緒にできるのではないかと思います。
――現状の取り組みに加えて、今後どのような取り組みが必要か?
- 本イニシアティブでは、管理職が率先して誰もが働きやすく休みやすい職場環境の実現を目指すイクボス活動を始めました。しかし、育児休業を取得した男性教員は本校でもまだ少ない状況です。小規模な大学ということで、周りに迷惑をかけてはならないという気持ちが余計に強いようです。研究室ごとに閉じられていて、一人が抜けるとやりづらさにつながっているのかもしれません。例えば、教員が複数講座を担当し合えるようにしたり、共通ラボで実験したりできるような、誰でも見られて、誰にでも相談できるような雰囲気づくりとともに、協力し合える人間関係づくりが必要です。さらに、休む人をフォローできる物理的なサポート体制の構築までしていかなければならなくなってきていると思います。
- 私自身、たくさん意見が出る会議のほうが有難く、より良い決断につながっていると感じています。もちろん多様な人材の集まりですので対立することもありますが、ダイバーシティ研究環境の実現に向けて、敬譲相和の精神を大切にしながら取り組んでいきます。
-
豊かな多様性を高い組織力につなげるために

日本医科大学
学長 弦間 昭彦 氏
日本医科大学と日本獣医生命科学大学、アンファー株式会社が協働してダイバーシティを実現する研究環境の構築に取り組む本事業は、中間年となる3年目を迎えました。ここまでの事業の成果、および残り期間に重点的に取り組むべき課題について、One Health実行委員長の日本医科大学・弦間昭彦学長に聞きました。(構成:木村麻紀/ジャーナリスト)2022年5月24日 インタビュー
―本事業は「女性研究者の研究力の向上・産学連携の促進」「女性研究者の上位職への登用促進」「社会全体としてのダイバーシティ環境の実現」という3つの目標達成に向けて、4つの行動計画に沿って取り組みを進めています。ここまでの進捗をどのように評価していますか。
4つの行動計画のうち「地域との連携によるダイバーシティ研究環境の実現」と「グローバル人材の育成」は、新型コロナウイルス流行の影響でかなり制限されましたが、「共同研究の推進と女性・若手研究者キャリア支援」と「上位職への登用促進に向けたキャリアアップ」については順調に進んでいます。
- 「共同研究の推進と女性・若手研究者キャリア支援」は、3つの組織の背景を踏まえて本事業の柱として位置づけられています。ライフイベントに直面する研究者をサポートする研究支援員を配置しながら研究費を活用してもらう仕組みで、本事業での研究費のほか、日本医大と日獣大との共同研究費も配分しています。公的な研究費を得るための講座の実施や研究計画書の添削支援の制度も設けており、女性も若手も多く活用しています。この制度を利用した人は翌年公的な研究費を獲得できている割合が高く、かなり有効に機能しています。公的な研究費を取るとモチベーションが高まりますし、その先のキャリアにもつながります。
- ―― 2つ目の「上位職への登用促進に向けたキャリアアップ」についてはいかがですか。
- こちらは、組織的な対応とともに、トップからの働きかけも行ってきました。具体的には、これまでは研究も診療も教育もすべて行えなければならないとしていた教授職の選考方法を見直し、秀でた部分を評価して登用する形に改めました。准教授、講師については研究を重視するとともに、ある一定期間は教育に従事する教育担当のポストを設けて女性を登用したところ、21名 (教授3名、准教授4名、講師14名) が昇任して数値目標を達成しました。ポジティブアクションの側面を持つ措置には一定の効果があったと言えるでしょう。
- さらに、女性教員のリストに基づきトップである私が直接面談して、昇進可能性のある人材の掘り起こしにも努めています。職位を得られそうな人材が志を維持できるよう面談をして、動機づけになればと考えています。
- ―― コロナ禍でのさまざまな制約が緩和されようとしている中、「グローバル人材の育成」や「地域との連携によるダイバーシティ研究環境の実現」もようやく進められそうですね。
- 「グローバル人材の育成」に関しては、コロナ禍でむしろオンラインでのカンファレンスなどを実施できる基盤が整ってきました。時差の制約はありますが、学生も対応できるようになってきました。海外との交流の敷居が低くなってきたので、今後さらに支援していきたいと考えています。留学経験のある研究者が中心となって、欧米を中心とした組織とのとのつながりを保ちながら公衆衛生や医療情報通信など何か一つの特定のテーマでモデルケースを作れることに期待しています。
- 「地域との連携によるダイバーシティ研究環境の実現」は、啓発活動が中心にはなりますが、活躍している卒業生との交流を促進させることにもつなげたいところです。活躍の場に気づくことや選択肢を広げられるという認識を持てることで、本学に戻って来ていただける機会にもなるかもしれません。また、日本医大が高大接続連携を結んでいる洗足学園高校をはじめとした高等学校での模擬講義など、教育を通じた次世代育成にも貢献して参ります。
- ―― 本事業は3つの別組織がダイバーシティという共通のテーマで推進している点も大きな特徴ではないでしょうか。
- 日本医大と日獣大とは同一法人であってもなかなか接点を持てませんでした。しかし、本事業を通じ各大学の中でも教員同士が諸課題に対して話し合えるようになっていると思います。例えば、日獣大が持つ食品領域は医療と直結しています。これからもさらに連携を強化していきます。また、アンファーという比較的新しい企業からも、アイデアや制度を色々と学んでいきたいと思います。
- ―― 本事業の後半期間で特に取り組むべき課題はありますか。
- ここまでプロジェクトを実施してきて、助教になるハードルが一番高いと感じています。ライフイベントが重なりがちですので、続けたいけれども困難を感じているのであれば、ご本人への支援やロールモデルの提示など、しあわせキャリア支援センターで行ってきていることをさらに周知していくことが大切です。幸いオンラインでの講座はじめ各企画への参加者も増えてきています。
- 育児休業等の取得で確かに周囲の負担は増えますが、社会全体として多様性への理解が進んできています。この時期のハードルを超えれば、研究助成金取れるようになり、職務的にも優遇されて講師、准教授への道も開けていくので、結果として女性登用が進んでいくと考えています。
- さらに、共同研究については多様なテーマを認めるとともに、後進への指導を通じて次の世代に還元してくれる人を積極的に支援していきたいと思います。
- ―― 本事業の後半期間のスタートに当たって、改めて今後のビジョンをお聞かせ下さい。
- 本事業は、多様性を認め合い組織力を高めていくことを目指しています。しかし、多様性があれば組織力が自然に高まるほど簡単なことではありません。個人の多様な人生のありようを前提に、個人は高いモチベーションを持っていかに組織で活躍するか、組織はそうした個人をどうポジショニングして活かしていくかを常に考えていかなければ、組織力を高めることにはならないと思います。活躍できるポジションは人それぞれで、時期によっても活躍できる領域が変わってきます。こうした部分を柔軟に活用し、組織を良くしようと考えていただける人を増やしていきたいですね。
- ここまで総じてうまくいっていますが、特に若手の層を厚くするにはどうすればいいのか、引き続き細かい工夫が必要です。最終的な目標達成に向けた戦略と戦術を、皆さんとご一緒に工夫しながら実行して参ります。
-
研究を辞めないで続けるための支援を
日本医科大学
微生物学・免疫学教室講師 若林 あや子 氏
現在、教室で食物アレルギーや腸管炎症の研究に携わりながら、しあわせキャリア支援センターで育児期の先生方へのサポート等を行っています。
私自身は息子が中学生になり手が離れましたが、小さな子どもを育てながら研究・教育・臨床を続けていくのは大変なことです。子どもの急な発熱などにも対処しなければなりません。女性教職員だけでなく、育児期の子どもを持つ男性教職員に対しても、この一時的に大変な時期のサポートをすることは大切です。最近行いました学内アンケートでも、育児支援を必要とする教職員が男女問わず多くいることが分かりました。大学や病院の大切な業務を担うそうした若い世代の方々にさらに声を上げていただいて、具体的にできることを形にしていきたいと考えています。
研究に関して言いますと、思わぬ方向・予想していなかった結果が得られることがあります。それも研究の面白さというか醍醐味です。私自身、予想していなかった研究結果が新たな発見に繫がったこともありました。また実験中にトラブルが起こることもあります。そうなると保育園のお迎えなど決まった時間に帰れないこともありますので、フレックスや時間外勤務可能な研究補助員の配置などのサポートも充実できればいいでしょう。研究で得られる刺激や醍醐味を多くの研究者に味わっていただけるような支援ができればと思っています。
研究結果は一朝一夕では得られず、多くの時間と労力を要します。研究を途中で辞めてしまうと新たな発見に至りません。それ故、家庭の事情などで研究の継続を断念せざるを得ない研究者に寄り添っていくような支援は、必ず大学全体の研究力の向上につながると信じています。
研究結果がひいては治療や予防の礎となり、様々な症状や疾患で苦しんでおられる患者様が一人でも減ることを願っています。私自身が食物アレルギーを持っており、アナフィラキシーの怖さ・苦しさも知っているので、患者様の力になりたいという想いがあります。
女性が働きやすい環境というのは、全ての教職員にとって働きやすい職場であると考えます。本事業を通じて、法人全体の働きやすさや研究力が向上し、患者様にもより一層喜んでいただけるようになればと思います。
-
動物をもっと身近にできる社会のために
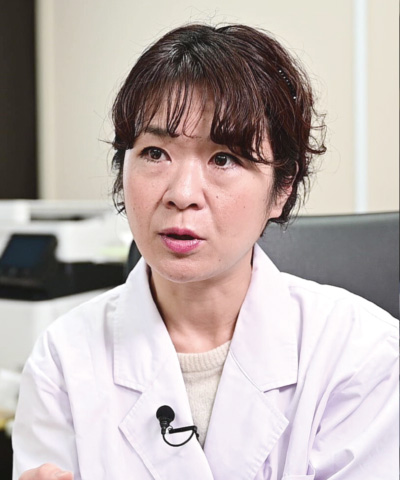
日本獣医生命科学大学
獣医学部獣医学科
野生動物学研究室講師 田中 亜紀 氏
日ごろ、動物虐待や災害時の動物の扱いなどをテーマに研究しています。米国に留学して研究生活を送りましたが、子ども育てながら研究するのは普通のことでした。日本ではまだ、子どもが生まれたらキャリアをあきらめるという傾向が強いかもしれませんが、向こうでは子どもがキャリアをストップする理由には全くならないと感じました。
米国での研究生活では、男女を意識することは全くありませんでした。上司は男性でしたが、子どもの学校が終わる15時半ごろになるとエレベーターで一緒になって、お互いに子どもを迎えに行く感じでしたね。
研究に集中できる時間が増えた
帰国後、日本では研究者が事務作業をしなければならないことが多くて驚きました。私も育児をしながらなので、大学に居られる時間が短い。大学に居る時間で研究したいにもかかわらず事務作業が非常に多かったので、支援員制度はとても助かっています。
支援員の方には9時半~15時ごろで、週に20時間の枠で来ていただいています。研究分野柄、視察など学外施設への出張が多いので、行くたびに領収書がたまり、帰るといつも事務作業に追われていました。今は支援員の方にやっていただいているので、とても助かっています。研究に集中できる時間が増えましたし、学生とのやり取りも増やすことができました。
一度は世界を見てほしい、そして育児があってもあきらめないで
日ごろ、動物虐待や災害時の動物の扱いについて関わっていますが、日本では動物を飼うことや家庭で受け入れることが、まだとても特別なことになっています。米国では、動物を飼うことはごく普通のこと。動物が社会にいることは普通でした。日本では、例えば災害時に避難所にペットを連れて行こうとすると問題になってしまいがちです。アレルギーの方もいるので、ある程度の区分けは必要ですが、もっと動物が社会の一員になっていれば、避難所に連れて行っても排除されることにはならないと思うのです。
研究留学は、やはり行って良かったです。日本にはない獣医学や、日本にはない研究分野がたくさんありました。学生にも言うのですが、一度は世界を見たほうがいい。やりたいことを制限するのではなく、今一歩踏み出してみるだけで、見えなかった選択肢がたくさんあることに気付けるので、まずは見てから選んでみるといいと思います。
また、結婚や出産をキャリアをあきらめる理由にしなくていいと申し上げています。私の姿を見て、育児があっても続けられると思ってもらえるといいですね。
-
保育支援制度で夫婦で仕事との両立が可能に

日本医科大学付属病院
消化器外科助教・医員 川島 万平 氏
私は肝胆膵外科を専門としており、他大学の皮膚科に所属してフルタイム勤務する妻との間に幼稚園に通う4歳の子どもがいます。一流の外科医、夫、そして父親になるべく日々奮闘しています。
当初は夫婦で平等に家事・育児をこなして仕事との両立を目指そう!と息巻いておりましたが、実際は私の帰宅が遅くなってしまい、妻への負担が大きくなっているのが実情です。妻には申し訳ないと常々思っており、家庭内の空気も不穏になりがちに―。何とか現状を打開できないかと考え、付属病院への転属を機に保育支援制度に申し込みました。主に子どもの幼稚園へのお迎えから、両親の帰宅までのシッターをお願いしています。
お陰で心に余裕を持って仕事ができるようになり、夫婦ともに仕事との両立が何とかできるようになりました。家庭にも平和が訪れた気がします。この形が正解なのかはわかりませんが、少なくとも保育支援制度がなければ仕事をセーブすることも考えなければならなかったでしょう。子どもを持つと、仕事と子育ての折り合いの付け方に悩まれる方も多いと思います。保育支援制度という選択肢があること知っていただき、高い志を持ちながら意に反してキャリアを中断してしまう人が一人でも少なくなることを願っています。
-
パートナーの職場のためにもなる
社会全体でのダイバーシティ推進を
日本獣医生命科学大学
獣医学部 獣医衛生学研究室准教授 落合 和彦 氏
日本獣医生命科学大学(以下、日獣大)で、ダイバーシティ推進委員会の副委員長を拝命しています。妻は私と同じく獣医師で農林水産省に勤務、小学4年生の長男と小学1年生の長女の4人家族です。妻もフルタイム勤務のため、子どもたちが急に熱を出したりしたときなどは、比較的時間に自由の利く私のほうが対応する場面が多いです。
ダイバーシティ推進委員として思うことは、真のダイバーシティ推進は「自分の職場内にとどまらず、パートナーとその職場にも波及するもの」でなくてはならないということです。
自分の職場で、子育てや介護に携わる同僚を助けることはもちろん大切です。しかしその結果、自分の家庭に充てる時間が減り、配偶者が思うように働けないようでは、社会全体のダイバーシティ推進は実現できません。私たちが学生の頃の大学教員といえば、「家庭を顧みず教育・研究に没頭し、配偶者は家で専業主婦」というスタイルが主流でした。しかし、令和の時代にそれは通用しません。父親も家事・育児を母親と同等にこなせなければ、家庭にストレスが蓄積していきます。
周りを見渡すと、家事・育児に積極的に参加している同年代の男性教員は、教育や研究でもしっかり成果を上げている方が多いように思えます。常に突発的な事案の発生への危機感を持ち、「明日も今日と同じように仕事ができるとは限らない」という気持ちで仕事に取り組んでいるので、当然能率は上がります。トラブルが無ければ、自分に課したノルマは時間内に余裕をもって終わらせることができ、余暇を子供と過ごす時間に充てたり、研究目標への更なるチャレンジに繋げたりすることができます。その結果、心にゆとりが生まれ、同僚を手助けすることもできます。これからは特に、若い教員が研究を能率的に進められるような環境づくりには力を入れたいと思っています。
最近嬉しかったのは、勤労感謝の日に長男が「お父さん、いつもおいしいごはんをありがとう」というカードをくれたことです。家庭で料理番を拝命し、ほぼ毎食ご飯を提供している父親としては感無量でした。それでも子どもは結局母親に懐いているので、今後は家庭での地位向上を目指していきたいところです。このような私ですが、後に続く皆さんにとって何らかの形でロールモデルになれば良いなと思っています。
-
研究支援員の派遣で効率アップ、新たな視点の提供も

日本医科大学
生化学・分子生物学(分子遺伝学)教室助教 笠原 優子 氏
私は、筋ジストロフィーでの細胞移植手術に向けた基幹研究をしています。幹細胞を用いて筋ジストロフィーの炎症を抑える新しい治療法です。研究者支援を受けさせていただいて、研究をサポートしてくれる支援員を派遣していただいています。
治療研究をしているのであれこれやってはみたいものの手が足りないので、せっかくの機会でもありますし、応募しました。実験が大変な時に手伝っていただけるよう、週2日フルタイムで来ていただいています。
一人でやっていると時間が限られて、夕方近くに時間的な制約が来てしまいますが、2人いると手が2倍になり、今まであきらめていたことを実現できるようになりました。協力していただけるので、仕事の効率も良くなりましたね。自分一人では気づけなかったことに対して、新しい視点を提案してもらったりするのも、とでも心強いです。
現在、小学生2人の子育て中です。家に帰ると研究から離れて、頭を切り替えて、けじめをつけないといけません。効率的に過ごすことも求められます。研究は研究、子育ては子育て。そのどちらも充実させたい。研究についてはサポート研究員を派遣していただいているおかげで、有意義な研究ができています。さらに、そのおかげで家庭では子育てに集中できるので、非常に助けていただいています。
個人的には治療研究を進めたいので、患者さんの治療に少しでも近づけるようにするのが夢です。社会に今何が求められているのかを見極めて、それを実現できるような研究者になることを目指しています。貴重な機会をいただいて良い研究環境を作っていただいているので、社会の役に立つ研究をしなければならないと思っている。
出産・育児の中でどうしてもあきらめがちなことがあると思いますが、研究に関してはあきらめないことが大切です。体力も時間も限られるので、効率的に進めないといけません。でも、子育てで大変なのは一時期です。だから負けないで、と後輩の皆さんにはいつも伝えているところです。
-
医師と研究者を両立しながら続けたい
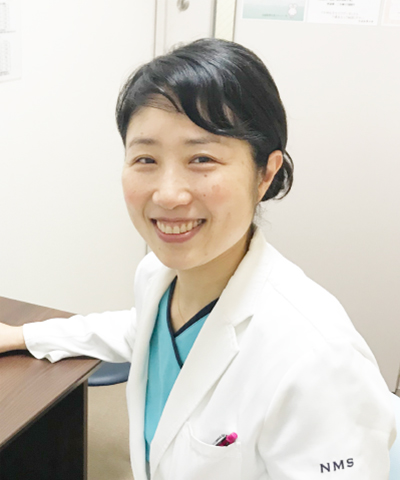
日本医科大学付属病院
女性診療科・産科助教・医員 市川 智子 氏
私は産婦人科医で、周産期と生殖医療を専門にしています。周産期はお産のお手伝い、分娩や帝王切開、妊婦検診、あるいは流産してしまった場合はその手術や心のケアです。生殖医療は不妊症や不育症の方をメインに行っており、特に体外受精では採卵や移植や子宮鏡もやっています。
研究としては、大学院で流産の研究をしたので、現在は子宮筋層の血流を超音波で評価させていただいています。血流を超音波で評価する手法があまり定着していないため、特定の超音波を使って、不育症で妊娠初期の方の子宮筋層血流を評価しています。血流の良し悪しと流産との関係を評価しています。
育児サポートのおかげで精神的な安心感
子どもは5歳と9歳です。休校期間中は、上の子どもはお弁当を持って学童保育に行っています。朝は保育園に送ってから出勤し、18時15分までに迎えに行かないといけないので、それまでに急いで仕事を終わらせて迎えに行きます。その後は夕食や上の子の勉強のサポートをして、寝る時間は23時頃です。
そのような生活の中で、私は毎週1回、同じシッターさんに自宅に来ていただく育児サポートを利用させてもらっています。食事作りから掃除、子どもの習い事の送りもやってもらっています。そのおかげで私自身がやらずに済むことが増えて、精神的にも休める安心感があるので、とても助かっています。もっと多くの皆さんが使えるといいと思います。
産婦人科医としての喜び
産婦人科は他の科の中で唯一、手術中に「おめでとうございます」と言える診療科です。もちろん悲しいこともありますが、概して喜びを与えられるのでとても素晴らしいと思っています。子供達も医者という職業に興味を持ち始めています。医者は常に勉強して新しい知識を入れて、ダイレクトに患者さんに活かしていくという職業ですので、勉強への意識は常に持ってもらって、精神的な部分は一緒にいる時間の中で育んでいけたらと思っているところです。
研修医制度が変わって、産婦人科医の激務ぶりが垣間見えてしまうことで敬遠してしまう人が増えているようです。もちろん生活の質も大切ですが、それだけを考えてしまうと、初めは良くても、時間がたつにつれて本人の意思が燃え尽きてしまって、医師自体を続けるのが困難になってしまいます。まずは、自分のやりたいことを優先にして邁進すれば、他の事は後から付いてくると思います。
研究のほうも続けたいですね。医師として色々な形がありますが、大学院で研究しながら新しいことが分かる喜びも経験したので、できるだけ続けたいです。後輩にも同じような経験をしてもらいたいので、自分も指導できる立場になりたいと思います。
文部科学省科学技術人材育成費補助事業・ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ
- 【牽引型】 2019 - 2024年
- 【女性リーダー育成型】 2022 - 2027年