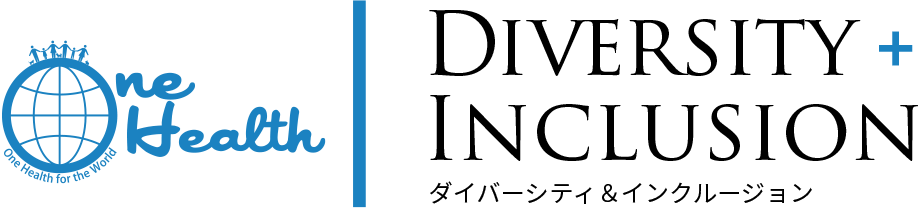-
『日々是好日 ~女性研究者として生きる~』Part1
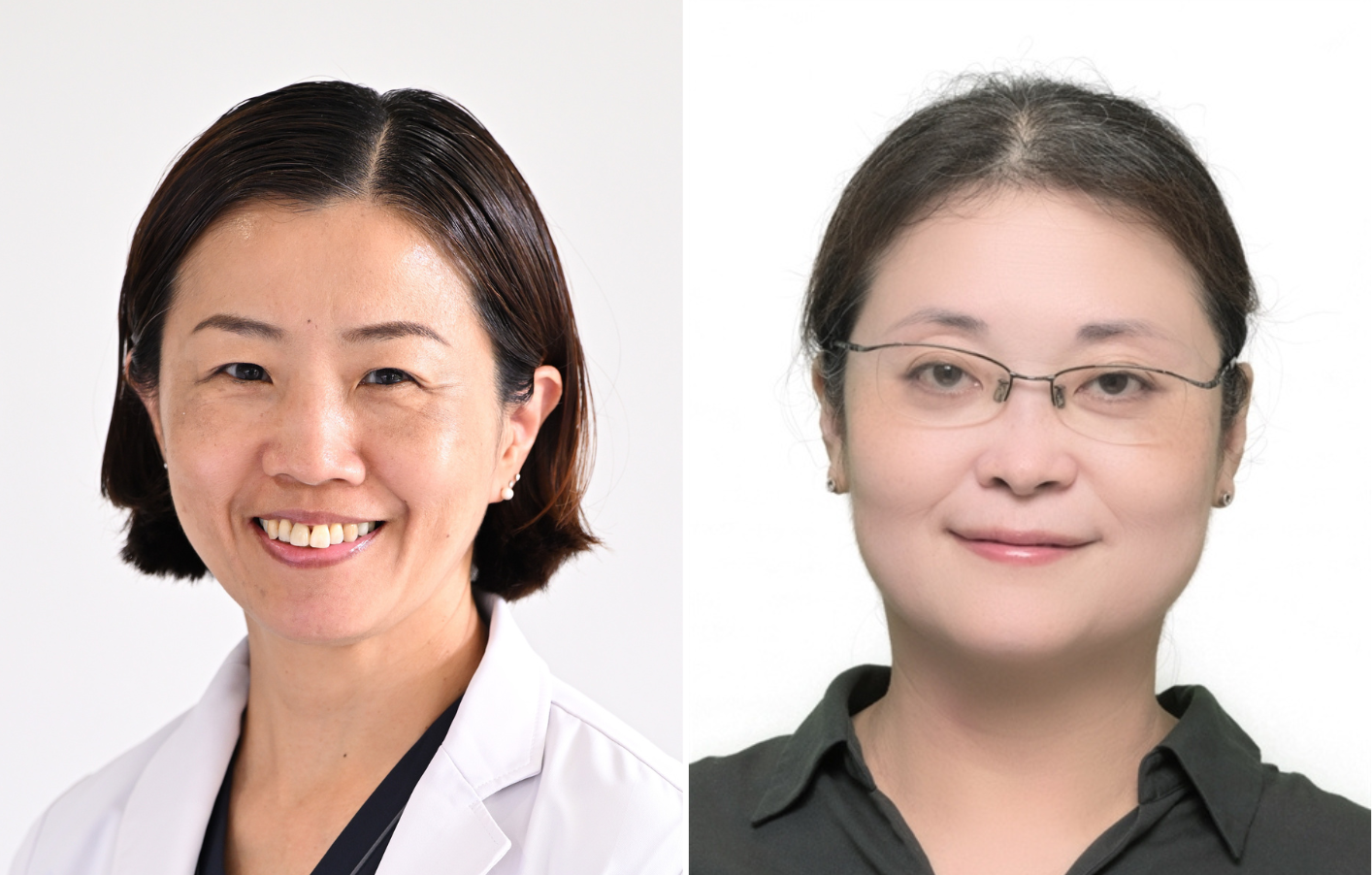
左:日本医科大学呼吸器内科学 教授(教育担当)
右:日本医科大学泌尿器科学 教授(教育担当) 谷内七三子氏 戸山友香 氏
Newsletterのコーナー『日々是好日 ~女性研究者として生きる~』は、日本医科大学、日本獣医生命科学大学の女性研究者にお話を伺い、研究やキャリア、ライフイベント、リーダーとしての役割など、等身大の想いや葛藤をご紹介しています。
- 今回は、日本医科大学呼吸器内科学 教授(教育担当)谷内七三子先生(写真左)、泌尿器科学 教授(教育担当)戸山友香先生(写真右)にお話をうかがいました。
- 構成:木村麻紀/ジャーナリスト
- 聞き手:米本崇子/日本医科大学総合医療・健康科学 准教授(教育担当)、One Healthニュースレター編集委員
- 2025年5月15日インタビュー

―お二人のご専門領域について教えてください。
谷内:分子病理の研究室で、肉芽腫性肺疾患における気管支肺胞洗浄に関わる研究で学位論文を書きました。その後子どもができまして、比較的自宅から近くて育児と両立できる大学の関連病院に派遣してもらって、臨床と育児を両立しながらバタバタの10年間を過ごしました。その間、派遣先の病院で慢性閉塞性肺疾患(COPD)の街頭啓発活動と疫学調査を行い、その成果を論文化しました。子どもが大きくなったタイミングで、2017年に大学へ戻りました。大学へ戻ってからは、喘息関連疾患の後ろ向き研究で論文を書きました。
戸山:泌尿器科の女性医師は少ないので、女性の疾患を担当するケースが自然と多くなりました。そんな中で女性泌尿器という分野が脚光を浴びてきまして、女性泌尿器を専門にするようになりました。その後、結婚して子どもが生まれ、その前後に医局長をやりながら復帰し、千葉北総病院へ行き、また子どもが生まれて復帰してという期間を経て、2020年に付属病院へ戻りました。
―私自身も含めて育児との両立に苦労しながら勤め続けてきましたが、育児と仕事の両立で、辞めたいと思ったことはありましたか?
戸山:教授に「もう厳しいから非常勤になりたいです」と言ったことがありました。教授に「何が一番困っているの?」と聞かれて、「そろそろ当直や祝日の日勤も再開するべきだと思うけれどもその見込みがたちません。」と伝えました。すると、教授に「もう1本論文を執筆して(当直が免除される)講師になるのはどうか」といわれたのです。そこで、当時もっていた女性泌尿器疾患のデータをまとめ、それが論文になりました。あの時が自分の人生の転機だったと思います。
谷内:私も辞めたいと言ったことがありますよ。戸山先生のように期限までに論文を書かなければならないといった明確なタスクを時間内にやるというのは、子育てをしたからこそ磨かれる面がありますね。逆に、子育ては思い通り、予定通りいかないことばかりで、そんな中で心が広くなると言いますか、許す、諦める、どこかで妥協する必要があるのを学べたのも、育児から仕事に反映できた部分かもしれません。
―ライフイベントから学んだこととして、タイムマネジメントや予想通りに行かなくても何とかやりきるグリッドやレジリエンスといった能力は、おそらく身についたのではないかと思いますね。
谷内:私に関して言えば、仕事と育児どちらも完璧を目指していません。50点、60点ぐらいって低すぎますかね(笑)、という感じでやってきました。あとはもちろん、周りのサポートがあるからこそ続けられています。
戸山:私が辞めなかったのは多分、自分の医局の雰囲気が好きだったからですね。尊敬する上司と一緒に働きたい、というモチベーションや、先輩後輩からサポートしてもらえたからこそここまで来れました。育児をしている後輩が多く、朝ごはんのメニューから夏休みの出かける先など、悩みも含めて分かち合えたのも救いでした。私は今でも日々必死で、自分が何点かなど考える余裕もなくて、とりあえず家を出るまでにできることだけやって、あとは自営業の夫に丸投げしています(笑)。有難いことに、夫は私の丸投げを一つ一つ拾ってくれます。
―下の世代から見ると、お2人は60点でもいいということや、夫に丸投げしてもいい(笑)、時短で教授というのもアリだと思える、夢を与える存在なのではないかと思うのです。
戸山:私の場合、自分の環境が私の希望する働き方にあわせてくださったので良かったのですが、人によってどのような環境が良いかは違いますよね。無理に引き止めないで、外に出るなら頑張って、と一度手を離したほうが良い関係が続きそのあとも助け合えたりします。逆に、大学に残りたい人については、どうしたら残りやすいかを一緒に考えてあげることはできるかもしれません。大学からも残ってほしい、残ってもらうために環境を調整しよう、と思ってもらえる人材になるための努力も日々求められると思っています。
谷内:今、いわゆる直美(臨床研修を終えた後、保険診療を経験せずそのまま美容医療に進む人)が毎年200人いるということが社会問題になっていますが、働き方として多様な選択肢があるということではありますよね。多様な働き方の選択肢があり、自分の進む道を選ぶことができる、ということが大切だと思います。
―本学のように女性を上位職に登用して活躍できる枠組みと雰囲気を作っておけば、若い先生たちが一旦外部に出ても、困った時にまた戻って来られるという安心感があるかもしれません。私は外部の病院勤務が長かったので、女性が上位職にいて、母船のような形で待っていてくれる教授がいるというのは、とても大切なことではないかと思っています。
さて、先生方のお子さんたちはもうだいぶ大きくなってきたのではないでしょうか?谷内:上の子は地方の大学へ進学し大学2年生、下の子は高校2年生ですが、海外留学しているので、2人とも家を出ていき、子育てもほぼ上がり、といった感じ。子どもと過ごした時間って、短かった…。戸山先生には、子どもが小さくて可愛い時期の子育てを楽しんでほしいなと思いますね。
戸山:ありがとうございます。上の子は小学生、下の子はまだ保育園児で全く余裕はありませんが、抱き着いてくれる今の時期をずっと覚えていたいと思います。
最近少し感じているのは、若い世代が大学に残りたいと思えるモチベーションをどのように引き出すかということです。今学位を取らない人が多いのですが、大学に残るには学位が必要です。でも、大学に残らなくてもいいから学位は取らない、と。
―実は、大学に残らなくても、外部の病院に部長職で行くとなると学位は必要です。また、子育てが終わって子育てで当直ができませんといった言い訳がなくなった時、臨床に加えて、戸山先生のように臨床成果を論文化するというのは、若い時にトレーニングを受けておかないと後輩に指導できません。上位職に就くには学位がないと戦えないということは、若い世代には伝えておきたいです。
戸山:そうですね。やはりやってみないと向き不向きも分かりませんから、とりあえず何でもやってみたほうが良い気はしますね。研究も論文もとりあえずやってみて1本書いてみないと「論文書くのに向いていないんだ…」ということも分かりませんしね。
―お2人はその時々で与えられたことを、自分の中で生かしながら今のポジションにつなげていらっしゃると思いますが、教授に昇進したことを活かしてこれからどのようなことに取り組んでいきたいと考えていますか。
谷内:医師を育てることやキャリア教育のほうに力を注いでいきたいですね。また、若い先生を育てる指導医の底上げにも取り組みたいです。昨年実施した教育担当FD(教育担当の教員を集めて、FDとしてワークショップを実施)のように、指導医同士で横のつながりを持ちながら悩みを共有し合えることで、大学全体が良くなっていくためのつなぎ役になれればいいのかなと思っています。戸山:キャリア教育で言えば、例えば医師には向いてないけれども研究者に向いている人もいますよね。目の前の人が何に向いているかを知り、その人の将来の選択肢を増やせるようなことができればいいなと思っています。まだ個人レベルでやっているだけで枠組みを作るところまではいきませんが、まずは自分が関われた学生や後輩だけでも、一番合っているものを一緒に見つけていきたいです。そうやって探していくうちに、本当にうちの大学のリーダーになっていく人が出てくるかもしれませんしね。メンター制度という素晴らしい制度がすでにあるので、それに加えて身近で小さなことでも相談できる環境があるとさらに良いのではないかと思っているところです。
文部科学省科学技術人材育成費補助事業・ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ
- 【牽引型】 2019 - 2024年
- 【女性リーダー育成型】 2022 - 2027年