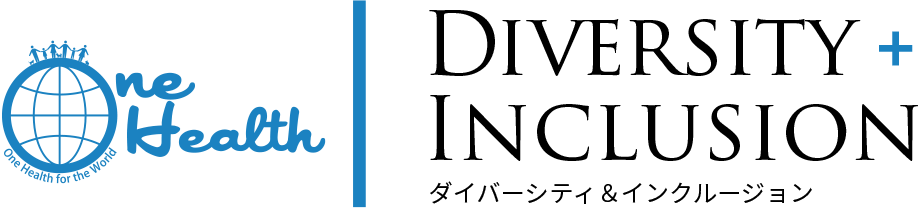-
女性研究者の活躍を支え、
次世代リーダーのすそ野を広げていくために
学校法人日本医科大学
しあわせキャリア支援センター センター長 土佐 眞美子 氏
学校法人日本医科大学しあわせキャリア支援センターは2019年の設立以来、本補助事業の牽引型と女性リーダー育成型を通じ、女性や若手研究者が育児などのライフイベントと研究・仕事を両立し、活躍できるよう支援してきました。牽引型が終了し、女性リーダー育成型が中間年を迎えた今、センターとしてどのようにリーダーを育成していくのか。土佐眞美子センター長に伺いました。(構成:木村麻紀/ジャーナリスト)
2025年5月28日インタビュー
自らのアンコンシャス・バイアスに気づく
センター長に就任して、7年目になります。ダイバーシティについて何も分からないところから活動を始めました。そのような私が研修で「アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見、思い込み)」を学び、まさに自分のことだと気づきました。それ以来、「できない」ではなく「どうすればできるか」と考えるようになりました。ゼロからの試行錯誤の連続でしたが、一歩ずつ歩みを進めてきた実感があります。若い先生方にも「どうすればできるか」と意識してほしいと伝えています。ダイバーシティ推進には困難もありましたが、理事長の深いご理解、両大学の学長のご尽力、センター運営委員の協力があり、ここまで進むことができました。また、4病院の院長をはじめ、多くの皆様のご理解とご支援にも深く感謝申し上げます。
女性リーダーが輝けるための支援と、次世代リーダーの育成を
2019~2024年度の牽引型では、主に育児・仕事の両立と研究支援を幅広く実施してきました。これらの事業は、大学の予算で今後も継続していきます。2022年度からは女性リーダー育成型が始まり、リーダーとして活躍する女性研究者と将来を担う若手研究者に向けた支援を行っています。
女性リーダー育成型はこのほど、中間評価にてA評価を受けました。女性教授職比率は、両大学とも20%を超え中間目標を達成しましたが、准教授、講師なども含めた女性研究者在職比率は、まだまだ目標に足りません。教授職に昇進した女性研究者の中には、急な抜擢や環境の変化に戸惑いを感じる方もいます。多くの方が控えめで誠実な姿勢を持ち、実力も兼ね備えているものの、リーダー職に求められる役割やネットワーク形成に不安を感じるケースがあると感じています。
医学部の入学者男女比はすでにほぼ半々であり、女性が十分に力を発揮できなければ、組織全体のバランスが崩れ、男性にとっても過度な負担が生じかねません。
一方で、女性リーダー育成の取り組みについては、まだ十分に理解が行き届いていない面もあると感じています。だからこそ、取り組みの意義を丁寧に共有し、すべての教職員にとって納得感と透明性のある制度設計を目指しながら、対話を重ねて進めていくことが重要だと考えています。
昇進はあくまで通過点であり、その後にいかに力を発揮し、自信を持ってリーダーとしての役割を果たしていただけるかが問われると考えています。FD(ファカルティ・ディベロップメント)や懇親会の開催を通じて、同じ立場の教職員が対話し、共感や相互支援のきっかけが生まれています。こうしたつながりが、リーダーとしての自信と成長を支える土台になると感じています。
「ダイバーシティって?」「しあわせキャリアって?」と言われていた頃から少しずつですが、認知度も上がってきました。研究支援への応募開始はまだか、といった問い合わせも増えてきましたし、不妊治療や介護といった重いテーマをランチタイムで話せるような会をやってみると反響があり、少しずつ浸透してきているのではと思います。男性教授との会話では「ダイバーシティってどういうこと?」といった反応は減り、女性のキャリアアップに関する相談も受けるようになりました。
先輩方の志を次世代につなぐ橋渡し役として
前身である「女性医師・研究者支援室」を導いてこられた先輩方の尽力により築かれた歩みが、現在の活動の礎となっています。医学・生命科学系に特化した大学法人でここまでの取り組みが継続されている例は稀であり、こうした先達の努力を次世代へと確実につないでいく“橋渡し役”を担うことが、私の使命だと感じています。
日本の女性は、若い人たちも含めて「一歩下がって」と思う人が多くいます。リーダー気質でなくてもその人に合ったやり方で、リーダーシップを取れるようになって欲しい。「どうすればできるのか?」を問い続けることで、自然にやりたいことに気づく人が増えれば、大学は今よりもっと活躍できる場になると思うのです。そんなリーダーコミュニティを整えた上で、後進にバトンタッチしていきたいです。
ダイバーシティという言葉を使わずとも、男性と女性、子育て中の人もその人を支える人も、お互いに認め合える関係性が理想です。今、日本医科大学は学生の半数以上が女性であり、彼女たちは5年後に卒業します。その時に、大学でキャリアを積むことを選択してほしいですし、そう思える環境に近づけていければと思います。
少子化や人材流動化が進む今、「選ばれる職場」としての大学の価値が問われています。誰もが安心して働き、やりがいを持って成長できる環境づくりを通じて、大学の未来をともに支えていきたいと思います。しあわせキャリアセンターの元々のミッションである、ここで働くことを喜んでもらえる環境整備のためにこれからも取り組んでいきます。
文部科学省科学技術人材育成費補助事業・ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ
- 【牽引型】 2019 - 2024年
- 【女性リーダー育成型】 2022 - 2027年