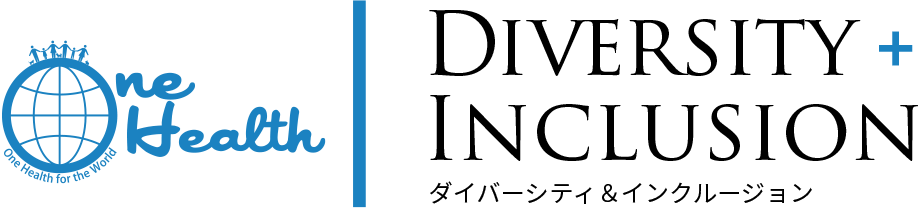-
医師と研究者を両立しながら続けたい
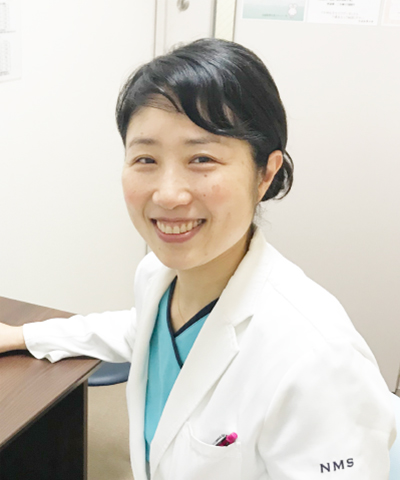
日本医科大学付属病院
女性診療科・産科助教・医員 市川 智子 氏
私は産婦人科医で、周産期と生殖医療を専門にしています。周産期はお産のお手伝い、分娩や帝王切開、妊婦検診、あるいは流産してしまった場合はその手術や心のケアです。生殖医療は不妊症や不育症の方をメインに行っており、特に体外受精では採卵や移植や子宮鏡もやっています。
研究としては、大学院で流産の研究をしたので、現在は子宮筋層の血流を超音波で評価させていただいています。血流を超音波で評価する手法があまり定着していないため、特定の超音波を使って、不育症で妊娠初期の方の子宮筋層血流を評価しています。血流の良し悪しと流産との関係を評価しています。
育児サポートのおかげで精神的な安心感
子どもは5歳と9歳です。休校期間中は、上の子どもはお弁当を持って学童保育に行っています。朝は保育園に送ってから出勤し、18時15分までに迎えに行かないといけないので、それまでに急いで仕事を終わらせて迎えに行きます。その後は夕食や上の子の勉強のサポートをして、寝る時間は23時頃です。
そのような生活の中で、私は毎週1回、同じシッターさんに自宅に来ていただく育児サポートを利用させてもらっています。食事作りから掃除、子どもの習い事の送りもやってもらっています。そのおかげで私自身がやらずに済むことが増えて、精神的にも休める安心感があるので、とても助かっています。もっと多くの皆さんが使えるといいと思います。
産婦人科医としての喜び
産婦人科は他の科の中で唯一、手術中に「おめでとうございます」と言える診療科です。もちろん悲しいこともありますが、概して喜びを与えられるのでとても素晴らしいと思っています。子供達も医者という職業に興味を持ち始めています。医者は常に勉強して新しい知識を入れて、ダイレクトに患者さんに活かしていくという職業ですので、勉強への意識は常に持ってもらって、精神的な部分は一緒にいる時間の中で育んでいけたらと思っているところです。
研修医制度が変わって、産婦人科医の激務ぶりが垣間見えてしまうことで敬遠してしまう人が増えているようです。もちろん生活の質も大切ですが、それだけを考えてしまうと、初めは良くても、時間がたつにつれて本人の意思が燃え尽きてしまって、医師自体を続けるのが困難になってしまいます。まずは、自分のやりたいことを優先にして邁進すれば、他の事は後から付いてくると思います。
研究のほうも続けたいですね。医師として色々な形がありますが、大学院で研究しながら新しいことが分かる喜びも経験したので、できるだけ続けたいです。後輩にも同じような経験をしてもらいたいので、自分も指導できる立場になりたいと思います。
-
研究を辞めないで続けるための支援を
日本医科大学
微生物学・免疫学教室講師 若林 あや子 氏
現在、教室で食物アレルギーや腸管炎症の研究に携わりながら、しあわせキャリア支援センターで育児期の先生方へのサポート等を行っています。
私自身は息子が中学生になり手が離れましたが、小さな子どもを育てながら研究・教育・臨床を続けていくのは大変なことです。子どもの急な発熱などにも対処しなければなりません。女性教職員だけでなく、育児期の子どもを持つ男性教職員に対しても、この一時的に大変な時期のサポートをすることは大切です。最近行いました学内アンケートでも、育児支援を必要とする教職員が男女問わず多くいることが分かりました。大学や病院の大切な業務を担うそうした若い世代の方々にさらに声を上げていただいて、具体的にできることを形にしていきたいと考えています。
研究に関して言いますと、思わぬ方向・予想していなかった結果が得られることがあります。それも研究の面白さというか醍醐味です。私自身、予想していなかった研究結果が新たな発見に繫がったこともありました。また実験中にトラブルが起こることもあります。そうなると保育園のお迎えなど決まった時間に帰れないこともありますので、フレックスや時間外勤務可能な研究補助員の配置などのサポートも充実できればいいでしょう。研究で得られる刺激や醍醐味を多くの研究者に味わっていただけるような支援ができればと思っています。
研究結果は一朝一夕では得られず、多くの時間と労力を要します。研究を途中で辞めてしまうと新たな発見に至りません。それ故、家庭の事情などで研究の継続を断念せざるを得ない研究者に寄り添っていくような支援は、必ず大学全体の研究力の向上につながると信じています。
研究結果がひいては治療や予防の礎となり、様々な症状や疾患で苦しんでおられる患者様が一人でも減ることを願っています。私自身が食物アレルギーを持っており、アナフィラキシーの怖さ・苦しさも知っているので、患者様の力になりたいという想いがあります。
女性が働きやすい環境というのは、全ての教職員にとって働きやすい職場であると考えます。本事業を通じて、法人全体の働きやすさや研究力が向上し、患者様にもより一層喜んでいただけるようになればと思います。
文部科学省科学技術人材育成費補助事業・ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ
- 【牽引型】 2019 - 2024年
- 【女性リーダー育成型】 2022 - 2027年